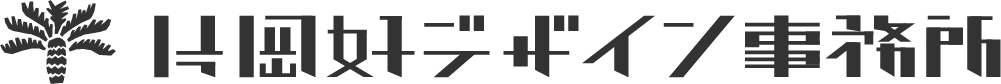モジャ! リターンズ
夏のVIVA! side A
Intro 90年代Remix
世の中には二種類の男が存在する。ビビる男とイバる男。
ビビる男は擦り切れる。
勝ち馬に乗ることだけを考えて、近視眼的損得で右往左往する。
イバる男は弛んで腐る。
椅子取りゲームに負けまいと、偽のオーラを不機嫌で演出する。
そんな時代はもう、うんざりだよね。
だよね〜DAYONE♩〜よくなくなくなくなくなくない?
フィッシュマンズも歌ってる。新しい人。呼んで、呼んで、呼んでよ〜。
お久しぶりね、あなたに会うなんて。
そうだね、今日は、新しい男の話をしよう。
ビビる男でもイバる男でもない。第三の男について。
それって、オーソン・ウェルズ?って、古っ。
こちら千代田区神保町、モジャ!リターンズ。
Track 1 Train Train
ていうか、夏。こっちは八月。そっちは?
日本のいちばん暑い日は、やっぱり残暑なんざんしょ。太陽が最も高く登る夏至はもう千年も昔のような水無月の頃なのに、今、2ヶ月ほどの時差ボケで地表が最高潮に温まる。なんだってそうなんだ。我々人類はバカ。いつも、その時に起こったことの意味がわからない。まぁ、それは当たり前なんだけど、困ったことについわかったふりをしてしまう。わかったふりをしておけばその場の空気を牛耳れる。賭けポーカーの常套手段だ。アクセルを踏む。早い者勝ち。あるいはクラクション。声がデカイ方に軍配。
いかんいかん、だんだん新聞コラムのような論調になってきた。俺たちにわかるのは、ちょっと先のことだけ。例えば、テーブルの上のアイスコーヒーの氷がもうすぐ溶けちゃうこととかネ。だから、いつだって後の祭りさ。捏ねた陶器の出来栄えは、釜を開けたところでわかりゃしない。今を、楽しもう。
そう、人の行動は、己の意思によるものだと思われている。だが、本当にそうなのか。そもそも俺が俺の意思をコントロールできているはずがない。それに、俺の意思が俺のものだとも限らない。情報操作は家庭の中、学校の中、職場の中、スマホの中、欲望の中、嫉妬の中、情報それ自体の中、俺自身の自己検閲の中に潜んでいる。何を言ってるんだと思うかもしれないが、何しろ俺は探偵だ。みんながスルーするところで、モジャつくことが生業なのだ。
意思は、思いつきに奪われる。それでいいよ、そうこなくっちゃ。面白がろう。線路は続くよどこまでも。朝起きた時、俺は床屋に行くつもりなんて毛頭なかった。毛頭なかったが毛根はあった。かつて日本人は、金髪の西洋人を毛唐と呼んだ。
事務所に向かう電車に乗ってたんだ。雨だったからチャリンコやめてトンネル抜けて。だけど雨はすぐ止んだ。俺はディスクマンを聞いていた。カネコアヤノが歌ってた。抱擁って歌を歌ってた。歌詞を読むまで俺は、それを放蕩だと思ってた。放蕩は、したい。抱擁は、されたい。今度猫を飼ったら、カネコって名前にしようと俺はぼんやり考えた。その時は、苗字じゃなくて名前みたいに、最初のカに、イントネーションを置いて呼ぶつもりだ。見たいモノだけ、見ているね。そんな気分になってるね。したいことだけしているね。そんな気分になってるね。それはとっても幸福なことだね。気づかないフリができるなら。
俺はスマホを使わない。今どき?ハハハ、おかげで形ばかりの友達は消えてったよ。便利なのに?イヤイヤ、進化はいつもトレードオフさ。俺たちは得たものだけに目を向けて、失ったものに気づかない。鳥は空を飛ぶために、骨の中を空っぽにした。重力に抗うために骨抜きの道を選んだ。スマホを見るより、電車の車内広告を見る方がマシだと思う。俺はね、俺は。だって顔を上げるし。頬の筋肉、垂れないよ。
夏の車内は、脱毛の広告に席巻されていた。ノースリーブの若い女が、バービー人形みたいにつるりとした脇の下を披露している。その隣では、また別の脱毛エステの広告がデカデカとしたゴシックの書体でいつでもどこでも予約が取れることをアピールしている。
しかし、ムダ毛という言葉は一体誰が作ったのだろう。ムダと言われりゃ、本当にムダな気がしてくるのが人の常。剃らなきゃって思っちゃう。デブとかブスとかっていう言葉もあるけれど、これは、ブって語感が強いよね。ブタのブ、おならの音もブ。なんとなく、それだけで貶められたような気分になる。
人は、自分のコンプレックスを指摘されると、克服しようと金を使うもんなんスよ。今の社会は不景気とはいえ何だかんだ裕福ッスから、曖昧な希望を語るより、日常のあかぎれ的な小さな傷口だって放っておいたら化膿ちゃうよ的に恐怖を煽る方が効くんスよ。
俺は、かつて飲み屋で同席したコピーライターの戯言を思い出していた。
脱毛広告の他に、唯一あったのは、増毛の広告だった。ATG、じゃなくてAGAか。夏は頭が蒸れたり紫外線を浴びたりするから、髪が抜けやすいんだという。ヘアサイクルが衰える40代、50代は要注意・・なんて書いてあるものだから、俺は一瞬、ドキリとしてしまう。別に気にもしていなかったことが、ちょっとした一言で、急にひどく気になってくる。この街にいると、四六時中カツアゲにあってるみたいだよ。東京シティ。
女は、毛をなくしたい。男は、毛を増やしたい。二つの相反するメッセージが都営新宿線の車内で同居する。女の脇毛を男の毛根に移植できる技術を開発したら、ノーベル賞がとれるだろうか。僕らはみんな生きている。なのに、みんな生きてることを恥ずかしがってる。
僕らはみんな歳をとる。なのに、みんな歳をとることから逃れようとしてる。
俺はさ、正直、脇毛のない女でも、脇毛のある女でも、どっちでもいいよ。歳とっているかどうかより、どんな風に歳をとっているかを見ているよ。支配者は、論点をずらし続けることで身を守る。言い出しっぺのわからなくなった政策を金科玉条に掲げ破滅に直進、雪崩を起こす。市民は現実に直面することに疲れ果て、思考停止するために酔っ払う。
本当のムダは、女の脇になんてないのさ。何年か前のフジロックで、コートニー・バーネットがホワイトステージで歌ってた。彼女は、脇毛を生やしてた。それは、チョイ悪オヤジのちょび髭とは別物だった。彼女の脇毛は、風に揺れる草原や馬のたてがみのようだった。
ロックだった。
リンダリンダズを聴こう。ロックは今、少女たちによく似合う。
もちろん、おじさんだって少女になれる。そんな風に生きてたら。
Track 2 必殺仕事人のテーマ
普段なら通り過ぎるところで立ち止まってしまうのは、俺の中の何かが変わった証拠。
綺麗な指してたんだね、気づかなかったよ。で、立ち止まったのさ、ユニーク。昭和の風情が残った理髪店。
俺は、いつもの道で、新しい出会いをした。そうだ、髪を切ろう。と思った。
理髪店で髪を切るのは久しぶりだった。半年に一度散髪に行くけれど、それはいつも美容院。俺は、俺がいつから美容院に通うようになったのか、もう思い出すことができない。昔は、男性が理髪店、女性が美容院と相場が決まっていた。それが今では、男の俺も、美容院の方が入りやすくなっている。トイレで座って小用を足す男性が増えているというけれど、そのうち女性トイレを使用する男性も増えたりするんだろうか。ジェンダーの多様化は、どこまで進むのだろうか。
理髪店に入るには、男としての気合というか、角ばった何者かが俺には足りてない気がする。いや、もしかして俺は、そのカクバリズムを避けたかったのかもしれない。
鏡ごしの理容師は、短髪オールバックの初老の男で、襟にパリッと強いアイロンのかかったワイシャツを着ていた。一方の俺は、アシカだかアザラシだかのイラストに、ASOVIVAとアルファベッドのロゴが入ったTシャツを着ていた。理容師の佇まいは、ジャンケンで言えばグー。俺のファッションは、今日もチョキ。理容師は黒のスラックス。俺は白と薄いブルーのタイダイジーンズ。
「今日はどうなさいますか?」と理容師が尋ねる。
オールバックの髪型は一糸乱れず、表情だけが柔らかく破顔する。
「あ、えーと」
俺がすぐに返答できないのは、髪を切りたいという欲求が先にあり、どんな髪型にしたいというイメージがないからだ。ビジョンはないけど、とりあえず立候補しちゃいました。だが、そこは相手がプロ。俺の曖昧な方向性を柔らかく受け止めて、
「今のイメージで、ちょっと軽くするくらいですかね」と微笑んでくる。
「あ、はい、今のイメージでお願いします」と俺は即座に返答するが、今の俺が一体、どんなイメージなのかよくわからない。わからないけれど、この人ならこの身を、いや、このモジャを委ねてもいいだろうと思わせる何かがあった。直感的にOKヨ。
「全体的に三センチくらい切って、夏ですし、少し、量を減らしときましょうか」
「あ、はい、それで」
俺は、理容師の提案が、まるでもともと俺が考えていたことと合致しているような気すらしてきた。だが、そんなことはあり得ない。だって、何度言うようだが、俺はそもそも何も考えてなどいないのだから。もう一度言う。自慢じゃないが俺は、いつでもどこでも、何も考えていないのだ。本当に何も。
理容師は、ガンマンのようなベルト付属の皮ポケットからハサミを取り出し、まず俺の後頭部の髪を人差し指と中指でひと束つまんでサクッと切った。それから、サクッ、サク、ササ、サッ、サ、ッ、と流れるような手技とともに音を変化させながら切り続けた。
俺は、鏡ごしにその姿を見た。
相変わらずオールバックは一糸乱れていなかった。口元には発掘されたての埴輪のような美しいアルカイックスマイルをたたえていた。
野球中継を見ていると、一流のバッターほどその表情は柔らかい。それはメジャーリーグ放送を見ていればよくわかる。
メジャーリーガーって、こんなところにもいたんだね。世の中捨てたもんじゃないね。SNSじゃ辿り着けないこの場所さ。
「こんな感じで、いかがでしょうか」
理容師の声で目を開けると、そこには芸術的な俺がいた。今だかつて、これほどまでに、証明写真を撮りたいと思ったことはない。 庭師がハサミを入れた日本庭園のようなモジャがそこにはあった。
俺は理髪店の最大の特典である顔剃りをしてもらいながら、この芸術的な手腕を持つ理容師に教えを請いたいと思った。何の教えかはわからない。ただ、教えが欲しかった。だが、そのきっかけがどうしても掴めなかった。物柔らかだが、やすやすと話しかけられない。理容師にはそんな風格があった。
俺は、素早く方針を転換する。自分から話しかけるのを諦め、相手が話しかけてくるのを待つことにしたのだ。相手が技をかけてきたその力を利用して、逆に技をかけ返す、柔道でよくあるあの要領だ。そこで大切になるのは、いざ相手が何か声をかけてきたとき、それを切り返す形でどのような質問をなすべきかである。時間は限られている。前段はいらぬ。気遣いやエクスキューズもいらぬ。単刀直入に、本質を突く質問を繰り出すのだ。
理容師は温かい弾力泡で包まれた俺の肌に、そっとカミソリをあて滑らかな手つきで産毛を剃っていく。おでこ、鼻、頬、顎。地球を一周するようにぐるっと航路を旋回し終えると、肌からそっと浮き上げたカミソリの刃を蒸しタオルで拭っていく。
そして、ついにおもむろに口を開いた。
「眉の下も、剃りますか」
理容師の問いかけは、俺の質問タイムのカチンコを鳴らした。
「ん、それは、ムダ毛ですか?」
いくら考えに考えてみたところで結局のところ無駄なのだ。どう転んだって俺の口から飛び出すのは、いつも出たとこ勝負の思いつきなのだから。
「え?」
理容師は、一瞬、戸惑うように黙った。ボールは、ラインを超えて誰もいないフィールドを転々とする。俺は、それを全速力で拾いに行く。だが、再びボールをキープしたところで、どこにゴールがあるのかわからない。俺が手にしているのは、このゲームの主導権だけだ。ルールも勝ち負けもない遠い国の戦争のような不毛なゲームの。
「あの・・・眉毛の下の産毛は、ムダ毛ですか?」
俺は、もう一度尋ねた。自分の口から出たその声を聞きながら、それがあたかも俺が最初から尋ねたいことであるかのように無理矢理思い込もうとする自分がいた。これでいいんだ。生きてゆくんだ。今、俺は、間違いなく、本質的な質問をしている。ただ、あまりに唐突だったから、相手も俺も動揺してしまっているだけなのだ。
「うーん、どうでしょうねぇ。ただ、眉の下の産毛を剃ると、目元の印象がクッキリします」
理容師は的確に答えた。わずかながら動揺が現れたのは最初のうーんだけで、すぐに物柔らかで冷静な口調に戻っていた。
立ち直りが早いのが私の長所です。かつてそんなCMがあった。ポカリスエットだった。宮沢りえだった。俺の口の中が渇いてきた。
サッカーの試合で負けたチームが、今日は自分たちの試合ができなかったというコメントを耳にするたび、「何を言っているんだ」と俺はツッコミを入れていた。
相手がいる時点で、その試合は、もう自分たちの試合ではないではないか。
自分たちの試合ができるのは、相手のいない独り相撲だけだろうと。
だが、その考えを、今、ここで撤回しようと思う。
理容師は、紛れもなく、自分の試合をしていた。ここに俺という相手がいて、すっちゃかめっちゃにかき乱そうとしているのに。
彼は、どんなボールでも受け止めて、理容師という彼自身のフィールドにきちんと置き直す。そして、一糸乱れぬオールバックで、ゴールキックよろしく自分の呼吸でボールを大空に蹴り上げる。
動揺していたのはむしろ、勝負を仕掛けた俺の方だった。相手が落ち着いていればいるほど俺は、自らの一挙手一投足が絶望的な失敗だったような気がしてアタフタとする。自分で自分を制御できなくなってくる。
「あの、私が言いたいのは、そういうことではないんです。私はね、ただ、ムダ毛を剃っていただきたいんです。ただ、何がムダ毛かわからないから困っているんです。だけど、それは、切ってみて、剃ってみて、初めてわかることだとも思うんです。剃った後に、あー、やっぱり、あれは必要だったなぁとしみじみ追慕するかもしれない。あるいは逆に、なんで早く剃っておかなかったんだろうと後悔するかもしれない。だからね、うん、いずれにしろ、剃らなきゃわからないんです、うん。だからね、今日は思い切って剃ろうと思います。剃った上で、ムダ毛なのか、そうでないのか、判断しようと思います。・・・例えば、そうですね。脇毛です。私の脇毛を剃っていただけますか」
Track 3 夕陽のガンマンのテーマ
試合結果は、ホイッスルが鳴る前から決まっている。
その日のコンディションをどうつくってきたか。これまでどんな練習をしてきたか。
「脇毛剃りは、やっていませんが」
理容師は、どこまでも冷静に答える。
「じゃあ、やってください」
俺は、もう引き下がることはできないと言葉に力を込めた。
「ほら、町の定食屋さんでも、メニューには載っていない裏メニューっていうのがあるでしょう。だから、それみたいに、お願いしたいんです」
俺は、きっと狂っているのだろう。だが、真実は狂気の中にのみ宿る。
「わかりました」
理容師は、覚悟を決めたように言った。
「ただ、別料金です」
「いくらですか?」
「三十万円です」
もちろん、それは高額だ。だが、俺は、理容師が俺の依頼を断りたいがために、高値をふっかけているのではないことがすぐにわかった。この人は、そんな風な価格のつけ方をする人間ではない。必ず三十万円の価値のある脇毛剃りをしてくれるだろう。
それは、もしかすると永久脱毛をするよりも高額かもしれない。剃った次の日から生えてくるにも関わらず。だが、それでも、お前には、その本気の脇毛剃りに三十万円を払う覚悟があるのか。問われているのは俺だった。
「カード使えますか」
俺は意を決して尋ねる。
理容師は眉ひとつ動かさず首を横に振る。
「申し訳ございませんが、うちはそのようなシステムがなくて」
それはそうだろう。ここは理容店だ。ペイペイは使えても、クレジットカードは使えない。それにそもそも、俺は、カードを持ってない。
ただ、俺に覚悟があることは、確実に相手に伝わったようだ。
いざとなれば、俺が、脇毛剃りに三十万を出す男だということが。
お互いの健闘をたたえ合うように、理容師はパンパンと心地よい音を立てて俺の肩をマッサージしてくれた。
俺たちは、いつの間にか旧友のように打ち解けていた。
「最後に、一つだけ伺ってよろしいでしょうか」
俺は、言葉遣いは丁寧だが、心はガブリ四つで理容師に迫った。
「もちろんです」
そう答える理容師のオールバックは、心なしか取組後の力士のように緩んで見えた。
「今朝、私は、思ったんです。世の中には二種類の男が存在する。それは、ビビる男とイバる男だと。これについて、どのような見解をお持ちでしょうか」
理容師は、俺の問いかけにしばし黙って考えた。マッサージする手は滑らかに俺の背中で動き続けていた。
「いや、あなたは男性の髪をカットする方だ。ですから、男性について一家言あるに違いないと思いましてね」
沈黙に耐え切れず俺は、自分の質問にエクスキューズを出す。
「で、お客さんはどっちなんですか?」
理容師がおもむろに口を開く。
「え、どっちって?」
俺は、初めて質問に質問返しされて、何を聞かれているのかわからなくなる。
「ビビる男とイバる男。どっちなんですか?」
俺は、この質問で、俺自身も男であることを思い出した。
人は、いつも自分の存在を度外視して、世界を分析する。
「うーん、どうでしょう」
俺は、ラジオの野球解説者っぽく言った。言いながら、思っていた。
どっちでもないものに、なりたいと。
「人間の頭皮は、二つとして同じものはありません」
理容師はそう言って続けた。
「髪もしかり。そして、それは、変わり続ける。同じお客様でも次に来店するときは、頭皮の状態も髪質も違っている。そういうものです。ですから私は、そのとき、そのとき、ベストな形でサービスさせていただこうと心がけております。
もちろん、常連のお客様の好みやご要望などは、しっかり記憶した上でサービスさせていただいていますが、あまりそれに捉われすぎると、何かが違ってしまうんです。いや、そもそもね、さりげないオシャレというものは、何気ない変化の中にあるんです。さりげない、何気ないって言うのはね、変わらないように変わるってことです」
そう言い終えたと同時に、理容師の手が俺の肩の上でピタリと止まりマッサージを終了した。オールバックの髪型は、いつの間にか、一糸乱れぬ状態に戻っていた。
その瞬間、俺は叫んでいた。叫ぼうなんてこれっぽっちも思っていなかったけれど、腹の底から湧き上がる温泉のような熱情に飲み込まれ、我を忘れて絶叫していた。
「ビバ!ビバ!ビバ!」
その声を聞いて理容師は、「お疲れ様でした」と鏡ごしに微笑んだ。
「あなたは、ビビる男でも、イバる男でもない。ビバる男です」
俺は、最大級の賛辞のつもりでそう言った。
理容師は照れ隠しするように、鏡ごしに合わせていた視線を下にそらして、俺のTシャツを指差した。
そこには、ASOVIVAと書かれていた。
VIVA!
(side Bにつづく)
ビーバーのTシャツ:
ロケ地:バーバーユニーク、味噌鐵 カギロイ(神保町)
テキスト:ミフキ・アバーチ
撮影:サマーカーター・トゥーイ
出演:ウーコ・カオターカ