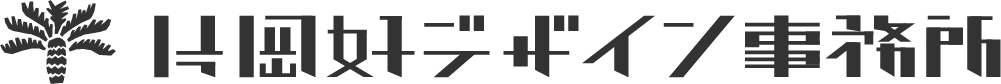モジャ!season2 第三回
ラ・フランス
その時だった。ふなっしーの皮が剥けたのは。
俺の脳内の、あるいは目前のふなっしーは、もう一枚ふなっしーを着込むと見せかけながら、着ぐるみの中で毛虫のように収縮し出した有機的な突起物をスーッと伸ばして後ろのチャックを膝下辺りまでズズズと下げると、お辞儀をするように真ん中から二つに折れてただの布切れとなった着ぐるみを脱皮する蝉のように脱ぎ捨てた。
蛹の中の幼虫は、体をドロドロのスープに溶かしてまるで別の生き物に生まれ変わるように再構成されるそうだが、変なおじさんとはまた違う意味で、変態と呼ばれる謂わば命のリサイクルを乗り越えて、ふなっしーの皮から現れたのは、まだ髪の毛の柔らかい少女だった。
「君の名は?」俺は、尋ねた。少女を怖がらせないように、緊張と加齢で毛羽立った声の表面を柔らかい布で滑らかに磨くようにして静かに注意深く発声しながら。
少女は、俺を見た。それは、まだ女の、いや、人の眼差しでさえなかった。母親の体液に塗れた生後間もない子鹿の目だった。薄い緑がかった色の瞳を見るのは初めてだった。
「ラ・フランス」と少女は言った。
「いい名前だね」と俺は少女が発する、まだこの地球上の空気を振動させることに慣れていないようなか細い声に魅了されながら少し間を置いて答えた。ラ・フランス。それが、いい名前かはわからない。ただ、もしも彼女がここで生きていくつもりなら、ちょっと変わったその名前を、厄介に感じることがあるかもしれない。彼女に対する恋心や嫉妬心、あるいは同じ土地の別の世界で暮らしている人間たちがすれ違いざまに吐き出すそれぞれの鬱屈が濃縮された排気ガスのような言動が、彼女を傷つけることがあるかもしれない。
けれど、名前を自分で選ぶことはできない。名前はいつだって与えられるものだ。たとえ、自分で考えたつもりでも、それは与えられたものだ。その証拠に、誰かに与えられ続けなければ、つまり呼ばれ続けなければ、その名前は煙のように消えてしまうのだから。
俺が少女に「いい名前だね」と言ったのは、生まれた時の名前のままで生きていくことへの憧れを、このふなっしーから生まれた少女に託してみたいという独りよがりの願望に過ぎないのかもしれない。あるいはただ、年齢も、性別も、目の色も、俺とはまるで違うこの少女と何を話していいかわからないから、彼女の名前を、たとえそれがか細い蜘蛛の糸のような手がかりに過ぎないとしても、途中でプッツリと切れてしまわないようにそっとつかもうとしたのだろう。
「それ、何の意味アンスか?」と首とスマホをタッチするための人差し指しかない若い引きこもりの地縛霊が俺の耳元で囁く。わかってるよ、俺だって君ぐらいの頃は、同じようなことを考えてたよ。だけど、やっぱり、たとえスーパーに行けない日でも、今、冷蔵庫に入っているもので料理してみようよ、と言ったら、地縛霊は「俺はイイや」と抑揚のない声で言って口元だけで冷笑した。
まぁ、そうだろうなぁ、若いもんね、いや、年齢どうこうの話ではないだろう。地縛霊の変異株は空気感染が早いのだ。でも、俺は君に何もできないから、とりえず『ベルリン天使の詩』見てよ、特にピーター・フォークのところ、と言って、俺は俺の時空に戻った。
「おじさんの名前は?」少女の声で我に返る。
「え?なんて」「おじさんの名前は?」少女は、さっきと同じことをまるで初めて言うみたいに言った。
「モジャ」と俺は答えた。
少女は、俺の瞳を覗き込むように見た。俺は、その目に見つめられることを受け入れた。本当の関係はそこからしか生まれないはずだから。
「モジャ・・・」少女はそう呟きながら小首を傾げると、「なんか違う」と言った。(続)
ロケ地:サツキ会館(神田小川町)
テキスト:ミフキ・アバーチ
撮影:サマーカーター・トゥーイ
出演:ウーコ・カオターカ