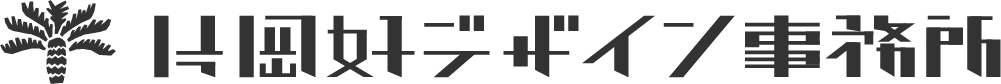「モジャ!」season1 最終回
また会う日まで
階段を昇れば、そこはポルトガル…ならぬアフリカだった。
初めてたどり着いたはずの扉には、サバンナ象が描かれた名札が架けられていて、その中央にはなぜか俺の事務所の名前が、まごうことなき俺の筆跡で記されている。
俺は、かつてここに存在していたのだろうか。二十万年前にホモ・サピエンスが誕生したアフリカの大地は、この事務所の入口と地続きで繋がっているのだろうか。
自分が生まれた時の情景を赤裸々に告白できない仮面なき俺は、あやふやで燃費の悪いモジャを抱え込み、なおもモジャって生きている。
戻ることもできるけれど、戻りたい場所もない。いわば、生まれた時からリストラされている、もっと言えば途方に暮れているのだと友川カズキが言うのなら、俺は勇気を振り絞るために、記憶のジュークボックスの中からBGMを選曲する。先の見えない不安とひとりぼっちの恐怖の中で俺を勇気付けてくれるのは、パンクロックだ。
クラッシュ、ラモーンズもいいけれど、日本語の歌詞で奮い立ちたい俺は、数年前のフジロックで見たイースタンユースの「ドンキホーテ」の曲紹介を小林克也風にして、目の前のドアノブに手をかける。だが、俺の胸に流れてきたメロディはパンタロンの昭和歌謡。
「また会う日まで、会える時まで〜」
俺は口ずさみながら、ドアノブを押す。不正解のブザー音がして、ドアは開かない。
「二人でドアを開けて〜」
サビの部分を歌いながらもっと強く押してみるけれど、やはりドアは開かない。「あ、引くんだ」と気がついた時には、もう別の歌を口ずさんでいた。
「涙くん、さよなら、さようなら涙くん。また会う日まで」
ドアはやすやすと開き、俺は酔っ払いのようにつんのめって部屋に入った。
「おかえり」と、あの女が言った。彼女は本物だったけど、本当じゃなかった。
Wi-Fi環境のないこの部屋で、ラインケーブルを通してマッキントッシュの画面に出現したズームの中で妖艶に微笑んでいた。
「私の依頼内容、わかった?」女が俺に尋ねる。
「わかる必要なんてあるのかい?」俺は尋ね返す。
画面の中の女は、ふっと笑って、スマホを取り出して電話をかける。全裸監督がカメラを操作しているのか、指や胸元や唇がアップになって、俺は湧き上がる雑念に殺られそうになる。
ダイヤル式の黒電話がリンリンと鳴る。「こんな骨董品のようなもの、事務所に置いてあったっけ?」と頼りない記憶をまさぐるが、今でもディスクマンを使っている俺だから、これくらいのことはやりかねない。
反射的に受話器をとって耳に当てると、穴粒の向こうから激しい吐息。パソコン画面に目を向け直すと、女がペットの豚の鼻面に受話器を当てている。
俺は笑った。女も笑った。誰かと一緒に笑うのは、久しぶりだった。
それは幸福と呼んでもいい代物だった。だけど本物の幸福はすぐに腐る。何しろ、そいつは生ものなのだ。保存料は一切使用しておりません。
だから俺は、女が話し出す前に電話を切った。パソコンも電源から引き抜いた。
今は、電話に出る時ではないのだ。どんなに高額の依頼でも。どんなに女が美しくても。
ただ俺は、散歩がしたい。くだらない雑学だけを喋っていたい。そして俺は、スーツから私服に着替えた。姿見で俺は俺を見て、もし生まれ変わったら、キングヌーの井口君みたいなファッショニスタになりたいと思いながら、窓から全力でジャンプした。
俺は、飛んでいた。電線よりも低い電柱色の空を。宮崎駿のアニメの主人公のようにふわふわと漂いながら靴下を脱ぎ、上空の雲を洗濯機に見立てて放り投げた。なんでそんなことしたのかは自分でもわからない。だけど俺は、自分にこんな汎用性のない能力があることに気づいただけで満足だった。役立たずは、誰にも支配されないから。
フェードアウトするように、視界が霧と闇に覆われる。
アスファルトの上にぶっ倒れている俺を見ているのは俺自身。ならば、俺はどこにいる?ならば俺は何者なんだ?
さよならだけが人生だ、って言ったのは、太宰治が悪人だって言った人。その人はね、太宰治より、よっぽど長生きしたんだよ。
アスファルトの地面に水溜りがあって、アゲハチョウが止まってた。
俺は、光に反射して映し出された水中の幻影を見ながら、俺の奥から何か、面白くて、美しくて、情けなくて、くだらなくて、懐かしいものが湧き上がってくるのを感じていた。
最後に、意味深長で謎めいた、女性の気をひくようなセリフが言いたかったけれど、俺の脳裏に音声付きで浮かんだのは、「駆け抜けろ、ドラゴンボール」というフレーズだった。
俺は、もう一度、黒電話の受話器を上げて、ダイヤルに指をかける。
今はただ、君の声が聞きたい。(終)

ロケ地:やっこ鮨(神田小川町三丁目)
テキスト:ミフキ・アバーチ
撮影:サマーカーター・トゥーイ
出演:ウーコ・カオターカ