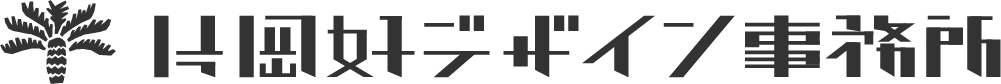「モジャ!」リターンズ 夏のVIVA! side B
Track 4 サマー・ソルジャー
俺は、居酒屋に向かって歩いていく。前から夏の湿った風が吹いてくる。
それは、電気カミソリで刈ったばかりの俺の新作うなじをくすぐりながら通り過ぎると、Tシャツの袖口から俺の懐へ入り込み、俺の脇毛をふわりと揺らした。
店に入った。誰もいなかった。勝手に入って適当に座った。少し待った。誰もこなかった。すいませんと呼んだ。反応はなかった。ビールくださいと言った。誰もこなかった。
目を覚ましたら、女がいた。あの女だった。
「なんか今日、感じ違う」女が言った。
「髪、切ったんだ。ビバってるだろ?」
俺は少し、いい気分になって言った。
「馬鹿ね」女が言った。
「どうして?」俺は尋ねる。
「なんでも、言葉にしないと、気が済まないんだもん」
俺はまたも、急所を突かれる。でもそれが気持ちいい。
「だから、言葉にできないことを見逃してしまうのよ」
女は、ノースリーブを着ていた。腕が閉じられていて、その脇は見えなかった。
「ビール、ください」
俺は、自分の敗北を認める代わりに注文をする。
「依頼するのは、私の方よ、探偵さん」
女は、そう言って立ち上がり、
「ま、いいわ、たまには、頼まれてあげる」
と言って、奥へと消えた。
俺は、女がビールを持ってくるまでに思い出そうとしていた。かつて女が俺に依頼した内容を。だけど、何も思い出せなかった。思い出せなかったけど、君に会えて嬉しかった。だけど、それを言葉にすれば、その喜びは恥ずかしさの中で消えてしまったり、何か別の物に変わってしまう気がして、俺は黙った。
俺は、立ち上がってステップを踏んだ。いや、踊れないよ。ただ、なんとなく、ステップ的な感じ。右足を前に出して引っ込めて、左足を前に出して引っ込める。今度は、右足を軸にしてくるりと回ってみる。つるつるの板の間だから、思ったより上手くいく。もう一回、今度はもっと早くやってみよう。
Track 5 HELP!
床にすっ転んで倒れたら、視線を感じた。いつの間にか、若い、女子大生くらいの二人組みが前の席で白ワインを飲んでいた。俺のビールはまだ来ないのに、どうして彼女たちには注文が来ているんだろう。女たちは、軽蔑するように向けていた俺への視線を素早くそらすと、「この白ワイン、なんか、ぶどうがすごい。うん、すごくぶどうがすごいよぉ」とよくわからない感動をしながら、二人で写真を撮り合っていた。
俺は、ちゃぶ台のような小机の前に、何事もなかったようにあぐらをかいて座り直すと、窓の外に視線を向けながら、女たちの会話に耳を澄ませた。
「ていうかさ、なんで、選挙権が18歳なのに、お酒は二十歳になってからなわけ?」
髪の長い方の女が言った。
「なんでだろう、まぁ、体の問題? ほら、まだ18歳は成長過程だから、お酒は有害なんじゃない医学的に。あ、でも、考えてみればさ、19歳の最後の日と、二十歳の最初の日で何が違うんだろうね。あ、ていうかさ・・・」
救急車のサイレンが、女たちの声を遮った。残念だった。俺は、彼女たちの会話に、司会者として参加したくなっていた。だって、楽しそうじゃん。
いや、ナンパじゃないです。交流です。ほら、もう、この歳でそんなね、下心とかないし。ていうか、百歩譲ってそれがあると仮定してもですね、彼女たちにとって自分は父親のようなおじさんだということは重々承知ですし、それを気づかずに勘違いしているオッサンが世間的に一番みっともないってこともよくわかってます。ですからね、これはナンパではありません。意見交換です。世代間の対話です。異文化交流です。
救急車が過ぎ去っていき、また女たちの声が聞こえてくる。会話の内容はいつの間にか変わっている。
「レディスデーって、あるでしょ」
グリーンのワンピースの方の女が言った。
「あー、あのレストランとか、映画館とか、安くなる奴?」
「そうそう、あれ、私、嫌いなの」
「えー、どうして?得じゃん」
「ちょっと、馬鹿にされてる気がする。優遇されてるってさ、一見、得しているように見えるけど、それって、相手の土俵にいるってことだよ。それってなんか・・・」
「たけやさおだけ〜」のリフレインが、再び女たちの声を遮る。俺は、彼女たちの批評精神に感嘆していた。与えられた情報を鵜呑みにするのではなく、客観的視点から再検証する能力。
実はね、前から言おうと思ってたんですけど、その彼女たちの批評精神っていう能力はね、実は探偵に一番必要なものなんです。うん、で、ね、これ、偶然なんですけど、そろそろ俺は、アシスタントが欲しいと思ってたんです。いや、今思いついたわけじゃなくて、本当に。ほら、彼女たちピッタリじゃないですか?
いや、だから、ナンパじゃないです。スカウトです。仕事の依頼です。いや、はい、確かに、世の中には、自分の好みの女性を秘書に雇うような、そしてやがて愛人関係になることを目論んでいるような、許せない男たちがいます。まあつまりそれは、イバる男たちです。最低ですよ、はい。公私混同ですよ、まったく。職権乱用です。ですが、私は違います。いつも同じ目線に立っていたいと思ってます。フェアトレードです。パートナーシップです。ウィンウィンです。
竿竹屋が過ぎ去っていき、三度女たちの声が聞こえてくる。会話の内容はいつの間にか変わっている。
「男女の平等って大切だけどさ、なんだって一緒にすればいいわけじゃないよね」
声の低い方の女が言った。
「わかるわかる、制服の問題とかもね、難しいよね。男女同じ服を着ればいいのかって言えば、そんなこともない気がするし、まぁ、体操着のブルマとかは論外だけど」
「そうそう、ハイヒールとかもね。女があれを履く意味、ある?ていうか、男だって、スーツにネクタイ、革靴の意味、ある?」
「うん、それもそうだしさ。あ、でもさ、脇毛はさ、やっぱ脱毛しときたいわけ、やっぱり私は。男は生やしてて、女は剃るものみたいな暗黙な了解があるけど、それはやっぱり、私は従いたいのね。いや、従うっていうか、あの、ジェンダーとか関係なしに、ただ、その方がしっくりくるの。あ、そうなの、今、言いながら思ったけど、私は、しっくりきたいの。何が正しいとかじゃなくてさ、しっくりくるかどうかなの」
「あ、それわかるー」
と思わず相槌を打ったのは、相方の女子大生ではなく、俺だった。
女子大生たちは、思わず振り返り俺を見るが、これは関わってはいけない奴だ的なコンマ2秒で目をそらす。
いや、ナンパじゃないです。シンパです、シンパシー。共感です。
俺は、女子大生たちの背中からビュンビュン飛んでくる軽蔑の矢印に耐えかねて、席を立ってトイレに向かう。廊下の先では、あの女が煙草を吸っていた。
「ビールまだ?」
俺はさっき起こった失態を編集でカットしようと、わざと大声で尋ねる。女は口から煙を吐き出しながら「休憩中」と答える。
休憩なんてビール出してからにすればいいじゃんと思ったけれど、いや、そういう働き方改革って逆にいいなって思い直す。
Track6 Sympathy for the Detective
女は、窓枠に両肘をつけて、外を眺めていた。その横顔がひどく美しかった。あ、二の腕も。女は、年齢不詳だった。少なくとも、さっきの女子大生たちよりは年上だろう。俺は、漁港直送のとれたての鮮魚より、炙りサーモンが好きなことを思い出した。あるいは、漬けマグロでもいい。
「その歳で、ナンパ?」
俺の行動の一部始終を見ていたようで、女は呆れ笑いを浮かべて言う。
「ん、な訳ないだろう。だって、娘のような子たちだよ」
図星を突かれた俺は、ギリギリの平生を装って言う。
「女はね、モテようとする男になんて興味ないのよ」
「え、そうなの? それ、どういうこと?」
女の言葉に素直に興味を持ってしまった俺は、恥を忘れて問いかける。今後の参考になりそうだから。
「モテようとするって言うのは、盛ってるってことなのよ。持ってるわけじゃなくてね」
文字で読めばすぐにわかる内容だけど、これを耳で聞いていた俺は、女が何を言っているのかを理解するまでにしばらく時間がかかった。
女は、タバコの煙をゆっくりと吐き出して言う。
「全部、見破られてるわよ」
あなたがモテない理由。それはキモチワルイからー。
俺は、女の唇から浮き上がっていく煙が夏の湿った空気の中に溶け込んでいくのを呆然と眺めながら、二村ヒトシの名著「すべてはモテるためである」の格言を思い出していた。
BonusTrack ロスト・イン・トランスレーション
「あ、ヤモリ」
俺は消え残って僅かに漂う煙が向かう天井を仰ぎ見てながら言う。
「え、どこ?」
と言いながら女は、俺の視線の先を見る。その視線につられるように、女の煙草を持つ指が、腕が、斜め上に上がる。ノースリーブの隙間から、女の脇が露わになる。
そこに、脇毛はなかった。代わりに、真っ赤な花が咲いていた。本物の秘密の花園だった。窓からの微風で、花びらがそよそよと揺れていた。異世界に足を踏み入れた俺は、言葉を失いそれを見つめた。
「何?」
女が尋ねる。俺にはまだ、この衝撃を翻訳するための言葉が見つからない。
「普通のことよ」
女は、俺の視線がどこに向いているかに気づいて言った。
「あなたが何も知らないだけで」
女の脇に咲いた赤い花は、生まれたての小動物がもそもそと指を動かすように花びらを広げると、中から黄色い雌しべをぬらりと伸ばして、首をもたげるように俺を見た。まるで雌しべの先端にもう一つの生命があるかのように。
そうだ、俺は、何も知らないのだ。この世界のことも。女のことも。何を依頼されているのかも。女の花から、芳しい香りがした。それは、夏の終わりを告げる香りだった。俺は蜂になって、その最後の蜜を求めて飛んでった。VIVA!(終)


ビーバーのTシャツ:
ロケ地:バーバーユニーク、味噌鐵 カギロイ(神保町)
lyric:ミフキ・アバーチ photo:サマーカーター・トゥーイ starring:ウーコカオ・ターカ